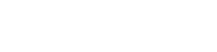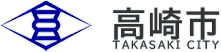本文
児童扶養手当
制度の目的
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることにあります。
受給資格
手当てを受けることができる人は、次の1~9のいずれかの条件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで手当てを受けることができます。
いずれの場合も、国籍は問いません。
※所得制限がありますので、申請者または扶養義務者の所得によっては、支給されない場合があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童(父または母の障害の基準)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
父または母の障害の基準
- 次に掲げる視覚障害
イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ
両眼中心視野視認点数が20点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 上記のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※厚生労働大臣が定めるもの
当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
支給されない場合
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
- 児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき。
母または養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童の父と生計を同じくしているとき。
※父が重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。 - 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。
※その配偶者が児童の父であって、重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。
父に関すること
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童の母と生計を同じくしているとき。
※母が重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。 - 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。
※その配偶者が児童の母であって、重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。
手当の支払い
手当は、認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
(例:1月期分は11月、12月の2か月分)
※手当額は、物価の変動に応じて毎年4月に変更されます。
手当額(月額)
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前の年の所得により、その年度(11月分から翌年10月分まで)の手当てが、次のいずれかの額になるか、全額が停止されます。
一部支給は、受給者の所得により10円単位で決定されます。
令和7年4月分から
児童1人の場合
全部支給:46,690円
一部支給:46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます)
児童2人以上の加算額(1人につき)
全部支給:11,030円
一部支給:11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます)
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 受給者本人(孤児等の養育者を除く) | 扶養義務者(及び孤児等の養育者) | |
|---|---|---|---|
| 全部支給限度額所得 | 一部支給限度額所得 | 所得 | |
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※受給者本人は、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族等1人につき15万円を所得額に加算
※扶養義務者は老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円を所得額に加算
所得の計算方法
児童扶養手当法でいう所得は、地方税法に規定する所得と養育費の8割相当額を加算した所得から、社会保険料相当額8万円と、次の控除のうち該当するものを引いた額です。控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。また、扶養親族の数も税の申告における扶養親族数です。年末調整や確定申告時には、扶養や控除の申告を忘れずに行ってください。
| 控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 寡婦 | 27万円 | 障害者扶養 | 27万円 |
| ひとり親 | 35万円 | 特別障害者扶養 | 40万円 |
| 障害者(本人) | 27万円 | 配偶者特別 | 相当額(33万円まで) |
| 特別障害者(本人) | 40万円 | 雑損・医療費 | 相当額 |
| 勤労学生 | 27万円 | 小規模企業共済掛金 | 相当額 |
父または母である受給者については、寡婦控除、ひとり親控除は控除されません。
公的年金等による支給停止
公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者又は児童が受けている場合や対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。
なお、障害年金を受給している場合は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することが出来るよう見直されました。
手続き
手当ての申請をされる際は、事前に窓口でご相談ください。
申請の際は、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、その他書類が必要となります。(状況により必要書類が異なります。)
※必要書類は、発行日から1ヵ月以内のものに限ります。
手当てを受けている方の届出義務
現況届
支給要件の審査をするために必要な届出です。
※毎年8月1日から8月31日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、11月以降の手当てが受けられなくなります。
※2年間届出がなければ時効により受給資格がなくなります。
額改定減額届 額改定増額請求書
支給対象児童の数が減ったときや増えたときに必要な届出です。
転出届
市外に転出するときに必要な届出です。
※転出先で児童扶養手当転入届の提出も必要です。
児童扶養手当変更届(住所・氏名・金融機関)
住所や氏名、振込先口座が変わるときに必要な届出です。
支給停止関係届
所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、本人または扶養義務者の所得更正がされたとき等に必要な届出です。
公的年金等受給状況届
受給者または支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や児童が公的年金の加算対象となったときに必要な届出です。
障害認定届
有期の障害認定を受けられている方が必要な届出です。
※診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月から手当ては支給されません。
証書亡失届 証書再交付申請書
手当証書を紛失したり、汚してしまったときに必要な届出です。
一部支給停止適用除外事由届出書
受給資格者(養育者を除く)が、手当ての受給から5年を経過する等の要件に該当したときと、その後の現況届時に必要な届出です。
※この届出をしない場合、手当ての半額を上限として、手当ての一部が支給停止となる可能性があります。
資格喪失届
手当ての受給資格がなくなるときに必要な届出です。
受給資格がなくなる場合は、主に次のとおりです。
- 受給資格者である父または母が婚姻したとき(事実婚を含む)
- 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所したとき
- 受給資格者である父または母が児童を監護しなくなったとき
- 受給資格者である養育者が児童と別居し養育しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
受給者死亡届
受給者が死亡したときに必要な届出です。
お問い合わせ先
- 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
こども家庭課 こども福祉担当 電話:027-321-1247 ファクス:027-324-1849
Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3492 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉303
倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3192 群馬県高崎市箕郷町西明屋702-4
箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055
Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658
群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381
Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-1392 群馬県高崎市新町3152
新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3392 群馬県高崎市下室田町900-1
榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112
Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-2133 群馬県高崎市吉井町吉井川371
吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133
Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp