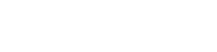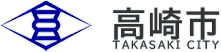本文
高齢者の新型コロナウイルス予防接種
市は、予防接種法に基づき、対象の方に新型コロナウイルス感染症の予防接種の費用助成を実施します。
※令和7年度の費用助成は、令和7年12月31日をもって終了しました。
令和8年1月以降に当該予防接種を受ける場合は、全額自己負担です。
助成期間
令和7年10月1日から令和7年12月31日まで
※医療機関が休診の日は外来での接種はできません。一般的に、12月29日から1月3日までは年末年始の休診期間となることが多いため、ご注意ください。
※助成期間内であっても、実施医療機関によってはワクチンの在庫の都合等により接種を終了している場合があります。事前にお電話等で直接医療機関へ接種が可能か確認してください。
対象者
高崎市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方
- 「接種当日」に満65歳以上の方
- 「接種当日」に満60歳から満64歳の方のうち、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(障害等級が1級か、同程度と医師に判断された方)
自己負担額
5,000円
ただし生活保護や中国残留邦人等への支援給付を受けている方は、無料です。
※令和7年度から国の助成が終了したため、自己負担額が変更になりました。
※助成が受けられるのは、期間内に1人1回のみです。
接種に必要な物
- 健康保険証(マイナ保険証、資格確認書等)
- 身体障害者手帳(60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器もしくはHIVによる免疫の機能障害があり、等級が1級の方のみ)
- 健康づくり受診券の新型コロナワクチン券(シール)
※令和7年4月1日以降に65歳の誕生日を迎えた方には同券がありませんが、接種を受ける際に保険証などで対象者であることが確認できれば、費用助成が適用されます。
※受診券の再発行を受けた方や転入され発行した方には同券の印字がない場合もありますが、接種を受ける際に保険証などで対象者であることが確認できれば、費用助成が適用されます。
※新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンと同時に又は間隔をあけずに接種することができます(医師が認めた場合)。
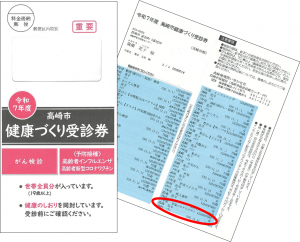
予防接種を受けられる医療機関
高齢者のインフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧
- 接種を希望する方は、医療機関に直接予約をしてください。
- 市外で接種希望の方は、別途お手続きが必要ですので事前(接種希望日の2週間ほど前まで)に下記フォームより申請するかに保健予防課までご連絡ください。
(電子申請)
申請フォーム<外部リンク>
ワクチンに関する情報
使用するワクチンについての情報などは、下記をご確認ください。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
各種相談・問合せ先
ぐんまコロナワクチンダイヤル(群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課内)
ワクチン接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な内容に看護師が対応しています。
- 電話:027-226-2615
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省)
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
- 電話:0120-995-956
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
制度をご利用になる場合は、事前に保健予防課予防接種担当(電話:027-381-6112)へお問い合わせください。
なお、現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>をご参照ください。