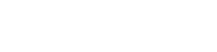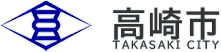本文
がけ条例(群馬県建築基準法施行条例第5号)について
群馬県建築基準法施行条例第5条(通称がけ条例)とは
群馬県では、がけの崩壊から人命及び財産を守るため、がけ付近に建築する全ての建築物を対象に、群馬県建築基準法施行条例第5条に基づき建築物の位置や構造等を制限しています。
「がけ」の定義
「地表面に対する角度が30度を超え、高さ2mを超えるもの」をがけとして取り扱います。がけに該当するかについては、計画地周辺の状況調査の結果をもとに設計者等(建築士等)が下記1~4などにより判定を行ってください。
- がけの判定の高さは、がけの下端からの 30 度勾配線を超える部分について、がけの下端よりその最高部までの高さとする。
- 地表面が水平面になす角度が 30 度を超える部分のうち、最も低い位置をがけの下端とする。がけの下に30度以下の勾配がある場合は、地表面が水平面に対しなす角度が30度を超える部分のうち、最も低い地点をがけの下端とする。
- 2段以上のがけがある場合は、がけの一体性を考慮し判断を行う。(県例規5-004参照)
- 既存擁壁等で建築基準法や宅地造成等規制法、都市計画法に基づく開発行為等による「検査済証」の交付を受けた既設の擁壁があり、設計者等が調査して経年変化や劣化等に対して安全上支障がないものは、構造上安全である擁壁に該当し、がけ条例の適用を受けるがけには該当しない。
がけ付近に建物を建てる場合には
がけに接して建築物を建築する際には、設計者等は、構造上安全である擁壁を設けるか、下記の県条例第5条各号のいずれかに該当する措置を行う必要があります。
- がけの上に建築物を建築する場合は、がけの下端から当該がけの高さの2倍以上の水平距離を設ける。
- がけの下に建築物を建築する場合は、がけの上端から当該がけの高さの2倍以上の水平距離を設ける。
- がけの形状、土質等によりがけ崩れのおそれがない。
「がけの形状、土質によりがけ崩れのおそれがない」とは、土質調査等により硬岩盤(風化の著しいものを除く。)であると確認された部分については、がけ条例の適用を受けるがけとはみなしません。 - 建築物の構造により被害を受けるおそれがないとき。
高崎市では他行政庁の扱いなどを参考にし、がけが崩れたとしても、その建築物が被害を受ける恐れのない構造(仕様基準)を策定しました。また、設計者等の構造計算等により安全が確認される場合も同様に扱います。
「がけ上」に建築する場合
がけ上に建築する場合は、がけ崩壊時においても建築物が倒壊することのない構造とします。具体的な構造についてはがけ上に建築する場合(PDF形式 442KB)を参照してください。
「がけ下」に建築する場合
がけ下に建築する場合は、がけ崩壊時においても崩壊した土砂等が建築物に流入することのない構造とします。具体的な構造についてはがけ下に建築する場合 [PDFファイル/302KB]を参照してください。