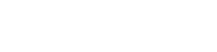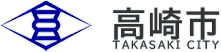本文
疥癬(かいせん)にご注意ください
例年、市内の病院や高齢者施設で疥癬の集団感染の報告があります。疥癬は診断が難しく、高齢者施設や病院等で集団発生が起こりやすいため早期発見・早期治療が大切です。
疥癬とは
疥癬はダニの1種であるヒゼンダニが人の皮膚に寄生して起こる感染症です。通常疥癬と角化型疥癬の2種類があります。潜伏期間は1~2ヵ月程度です。角化型疥癬の場合は4~5日の場合もあります。潜伏期間が長いので発見が遅れがちです。
| 通常疥癬 | 角化型疥癬 | |
|---|---|---|
| ヒゼンダニの寄生数 | 数10匹以下 | 100~200万匹 |
| 患者の免疫力 | 正常 | 低下している |
| 感染力 | 弱い | 強い |
| 主な症状 | 赤いブツブツ(丘疹、結節)、疥癬トンネル(曲がりくねった線状の皮疹) | 厚い垢(あか)が増えたような皮膚(角質増殖) |
| 痒み | 強い | 不定(痒みがないこともある) |
| 症状が出る部位 | 頭や顔を除く全身 | 全身 |
感染経路
通常疥癬
長時間、肌と肌が直接接触することで感染します。また雑魚寝をしたり、寝具・衣類を共有することでも感染します。
角化型疥癬
感染力が強いため、短時間の接触でも感染します。寝具や衣類を介した感染だけでなく落屑(らくせつ)(皮膚から剥がれ落ちたかけら)にも多数のヒゼンダニが含まれるため、それらに接触することでも感染します。
疥癬が疑われるときは
夜間に強くなる痒みや皮膚症状があり、疥癬が疑われるときはすぐに皮膚科を受診しましょう。
疥癬の治療
飲み薬や塗り薬により、ヒゼンダニを駆除します。医師の指示に従い、決められた期間治療しましょう。
疥癬と診断された場合の対応
通常疥癬と角化型疥癬は感染力が違うため、対応方法も異なります。
通常疥癬
- 患者の隔離は不要です。
- 清掃、洗濯、入浴、リネンの交換は通常どおりで問題ありません。
- 長時間、肌と肌が直接接触することは避けましょう。
- 雑魚寝をしたり、寝具・衣類など肌に直接触れるものを共有することは避けましょう。
角化型疥癬
- 目安として治療開始後1~2週間までは隔離が必要です。患者と接するときは長袖ガウン・手袋を着用しましょう。
- 清掃は落屑を残さないように掃除機をかけましょう。
- 洗濯は他の人の洗濯物と分けて洗濯後に乾燥機を使用するか、洗濯前に50℃で10分間熱処理をしましょう。洗濯物は落屑が飛び散らないようにビニール袋等に入れて密閉して運搬してください。
- 入浴は最後とし、使用後は清掃しましょう。脱衣所は掃除機をかけてください。
- リネン類は毎日交換しましょう。
- 殺虫剤(ピレスロイド系を推奨)は治療開始時に安全性に配慮したうえで1回散布します。毎日散布する必要はありません。
- 治療終了後の部屋は2週間閉鎖するか難しい場合は殺虫剤を1回だけ散布しましょう。
施設の方へ
- 外部(利用者、職員、面会者など)からのヒゼンダニの持ち込みにより、多くの場合ヒトの手を介して感染拡大します。そのため、特に新規利用者に皮膚症状がないか家族や前の施設・病院の職員に確認することが大切です。
- 入浴・清拭時や普段のケア(衣類交換など)の際に利用者の皮膚を観察しましょう。
- 利用者で疥癬が疑われる場合は、他の利用施設(デイサービスやリハビリ等)、かかりつけ医、転出先等への情報提供を行ってください。
- 感染が疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生したなどの場合は、保健所への報告が必要です。
報告については「施設等における感染症集団発生の報告について」をご覧ください。
関連情報リンク
- 疥癬とは(国立健康危機管理研究機構)<外部リンク>
- 皮膚科Q&A 疥癬(日本皮膚学会)<外部リンク>