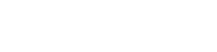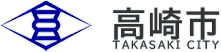本文
予防接種とは(予防接種の意義や仕組み)
予防接種を受けましょう
赤ちゃんがお母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)は、感染症の種類にもよりますが生後3か月~生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもは発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種の正しい知識を身に付けて、予防接種を受けましょう。
「予防接種と子どもの健康」(小冊子)について
この冊子は、予防する病気の説明やワクチンの特徴・副反応などがわかりやすくまとめてあるものです。予防接種を受ける前に必ずこの小冊子や市から配布されるお知らせ・予診票の裏面等を読みましょう。高崎市保険年金課又は各支所の市民福祉課の他に、高崎市保健所保健予防課(高崎総合保健センター内4階)及び各地域の保健センターにも置いてあります。
ワクチンとは
感染症の原因となるウイルス、菌、細菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。予防接種に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。細菌やウイルスの性質によってはワクチンが作れないものもあります。ワクチンは大きく2種類に分けられます。
生ワクチン
生きたウイルスや細菌などが含まれていますが、弱毒化(病気を起こす性質を弱めていること)されています。生ワクチンは比較的長く持続する免疫ができるといわれています。
該当するワクチン
BCG・麻しん風しん混合(MR)ワクチン・水痘ワクチン・ロタワクチン・おたふくかぜワクチンなど
不活化ワクチン
生きたウイルスや細菌などは含まれておらず、予防接種を受けた後も体の中で増えることもないので、1回の予防接種では十分な免疫ができないことが多く何回か予防接種を受ける必要があります。また、免疫が持続する期間は生ワクチンと比較すると短くなります。
該当するワクチン
ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン・四種混合(DPT‐IPV)ワクチン・B型肝炎ワクチン・日本脳炎ワクチン・HPV(子宮頸がん)ワクチン・インフルエンザワクチンなど
異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔について
生ワクチンを接種したあと別の種類の生ワクチンを接種する場合には、4週間の間隔をおきましょう。
※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれに定められた間隔があるので、間違えないようご注意ください。予防接種のスケジュールについては、かかりつけの医師とよくご相談ください。