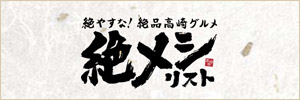本文
特別インタビュー 指出一正さん (2)
![[写真:指出一正さん]](/uploaded/image/15758.png)
高崎市が「関わりしろシティ」を宣言してくれるといいですね。
−指出さんは人口減少対策のソリューションとして「関係人口」という概念を提唱されました。さらに関係人口を増やすためには「関わりしろ」が必要で、そこには「自分ならこうするという内発性や創造性を誘引するザラザラ感がある」と指摘されていますね。
街のサービスが全て行政主導で行われている所では、関わりしろは生まれづらいのです。自分事として街を考えている世代の人達が少なからずいることが、街がおもしろくなる大きな要素です。
高崎では学びの場として「ジョウモウ大学」※(入学金や授業料のない市民大学)をつくった皆さんや、それを受け継いだ若い世代が素敵なお店を作ったり、プロジェクトに関わったりしているので、ちゃんと関わりしろのある街だなと思います。冷静にいろいろな街を拝見している中で、街づくりがおもしろい方向にいっている街のひとつと捉えています。
※2020年7月をもって活動は終了しています。詳細はジョウモウ大学のホームページ<外部リンク>へ
−ザラザラ感にはどのように着眼すればよいのですか?
完璧に隙間を埋めてしまうような構造ではなく、誰かがその隙間に対して、何かをやってみたいなと思う空間や時間があるかどうかだと思っています。例えば官や企業主導でイベントが開かれていれば、僕たちはいつまでもお客様のまま土曜・日曜を費やしてしまいます。それも確かに楽しいとは思いますが、中には物足りなさを感じる人達もいます。
自分がこの街で暮らしているとか、自分がこの街の主体のひとりだと思うことが、じつは軽やかな生存確認にもつながるんですよね。だから「○○さんがいてくれて良かった」という言葉がどれくらい生まれるかが、関わりしろのひとつの基準です。
プロジェクトの仲間として、お皿洗いをする男の子がいるとか、道路で何かを販売する女の子がいるとか、ふわりと日常の中で何かの役目を任されることが連続して起きているかどうかですね。高崎市が「関わりしろシティ」を宣言してくれるといいですね。
街に古民家や空きスペースがあって「1週間なら貸してあげるよ」とか、突然やってきた人にも「皆で使っていいよ」という関わりしろがあると、街がおもしろくなっていきます。
−指出さんは「関わりしろがとりなすのは弱さの交換」と持論を展開されていますが、「弱さの交換」とは何でしょうか。
お互いに困ったなという課題をどんなコミュニティでも持っています。俺たち年を取っているなとか、仲間が減っているなとか。年を取ればグループの中に変化が起きて、今までできていたことができなくなったという課題が、個人だけでなくコミュニティにも起きています。道普請をやりたいけど人が足りないないとか、雪かきが大変だとか。その一方で、若い人達がマウンテンバイクやスノーボードで遊ぶ場所を探しているけど、大人達が理解してくれないという問題があります。お互いに弱いものを持っていて、その弱いものを交換して、例えば「うちの裏山が空いているから、スノーボードをやってみたら?」と言えば、若い人達が喜んで遊びます。
そこで人間関係が縮まると、見えていなかった弱さが見えるようになって、人の心を感じ取れるようになります。若い人達は感覚が鋭敏なので、その地域で困っていることを感じて、何か役に立つことをやりましょうかと。そして道普請や雪かきを手伝って、弱さの交換がなされるわけです。
![[写真:指出一正さん]](/uploaded/image/15759.png)
−高崎市が関係人口を増やすためのポイントは何だとお考えですか。
高崎市という主体が高崎市に関わることで何が起きたら一番うれしいのか、幸せなのかを考えることが大事かもしれませんね。そのためにどんな人達が関わってくれたらいいかというバックキャスティングが必要です。僕は「高崎市は10年後にどうなっていたいんですか?」と聞いてみたいですね。
例えば愉快な未来を創りたいのか、胸熱な未来を創りたいのか、大阪並みにボケとツッコミのできる未来を創りたいのか。そういうことがグランドビジョンになるんです。高崎駅を降りて皆から「よく来たね」と言われたら、関係人口は絶対に増えます。