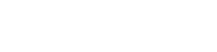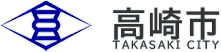本文
長期優良住宅建築等計画の認定について
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
1.長期優良住宅建築等計画等認定制度の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した住居環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、認定計画実施者が建築及び維持保全を行うこととなります。
2.高崎市の長期優良住宅の認定基準
住宅の規模の基準(法6条1項2号)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律省令第4条のとおりです。
※高崎市は地域の実情を勘案して定める面積の定め(緩和)はありません。
最低基準
住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上
一戸建ての住宅の場合
床面積の合計が75平方メートル以上
共同住宅等の場合
一戸の床面積の合計が40平方メートル以上
住居環境等の基準(法6条1項3号)
高崎市では高崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(例規集)第2条より、法6条1項3号の認定の基準を定めています。
次に掲げる事項等に適合させてください
- 地区計画の区域内における取り扱い
地区計画の概要(問い合わせ先:都市計画課) - 建築協定の区域内における取り扱い
建築協定の概要(問い合わせ先:建築指導課) - 景観条例の取り扱い
景観条例の概要(問い合わせ先:都市計画課)
次に掲げる区域内は認定をしないものとします
- 都市計画施設の区域(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設内)
道路、公園、河川等が該当します。例えば、都市計画道路の予定がある場所は認定できません。 - 市街地開発事業の区域(都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業区域)
土地区画整理事業や市街地再開発事業の区域内等では認定できません。
ただし、施行区域内であっても建築物が長期にわたり立地が可能と想定できる場合(仮換地指定されている区画整理地で土地区画整理法第76条許可を得ている場合等)はこの限りではありません。
長期使用の基準(法6条1項4号)
高崎市では高崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(例規集)第2条の2(令和4年4月1日施行)より、法6条1項4号の認定の基準を定めています。
次に掲げる区域内は認定をしないものとします(令和4年4月1日以降)
地すべり防止区域・土砂災害警戒特別区域・急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)(いわゆるレッドゾーン)では、認定できません。
ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、これらの区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちにこれらの区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りではありません。
3.認定申請について
認定申請にあたって、確認登録住宅性能評価機関の、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を受ける場合は、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書等を添付することとなりますので、確認書等に関する手続きについて、各登録住宅性能評機関へもお問い合わせください。
建築基準法第42条第2項に規定する道路に接している場合は事前に生活道路拡幅協議を行ってください。
※高崎市では確認書等の利用を強く推奨します。
※高崎市では確認書等と確認済証を同一機関から認定申請前に取得することを推奨します。
※高崎市では適合審査の申出(法6条第2項)の利用を推奨しません。
※確認書等とは、品確法第6条の2に基づく、登録住宅性能評価機関が当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面(確認書)、若しくは住宅性能評価書(長期使用構造等への適合の確認が行われたものに限る)のことです。
4.手数料・受付時間
手数料
受付時間
- 受付場所:建築指導課(本庁11階)にて受付手続きとなります。※都市計画課の経由が必要となります。
- 受付日:毎日(土曜日、日曜日、祭日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後2時30分
終了時間間際の場合は受付にならない場合もございます。時間には余裕をもって来庁してください。
5.長期優良住宅に係る変更
長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅に係る変更等が生じた場合は、速やかに、変更の手続きを行う必要があります。
変更申請等については以下のものがあります。
- 法第8条第1項による変更認定申請
- 法第9条第1項による譲受人を決定した場合における変更認定申請
- 法第10条による地位の承継を行う場合の申請
- 省令第7条各号に該当する軽微な変更に係る届出
6.工事完了報告
長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅に係る工事が完了した場合は、速やかに、建築工事が完了した旨の報告を行う必要があります。
なお、工事完了報告書「5.軽微な変更の内容」には軽微な変更届の提出が不要な内容のみ記載してください。(例:配置の変更、分合筆による地名地番の変更、敷地面積の変更等)
報告については、下記の書類を提出してください。
- 工事完了報告書 [Wordファイル/29KB]、工事完了報告書 [PDFファイル/57KB]
- 工事監理報告書(建築士法) [Wordファイル/46KB]、工事監理報告書(建築士法) [PDFファイル/71KB]
- 認定通知書の写し
- 検査済証の写し
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
7.認定長期優良住宅の建築・維持保全に係る記録の作成及び保存
- 認定計画実施者(建築主・分譲事業者や認定住戸の買主等)には、認定長期優良住宅の建築や維持保全に係る記録の作成及び保存に関する義務があります(法11条)。
- 認定計画実施者が長期優良建築等計画等に従って維持保全等を行っていると認める証拠となりますので、特に認定長期優良住宅を購入された方は、適切な作成・保存をしてください。
8.よくある質問
関連リンク
国土交通省長期優良住宅<外部リンク>