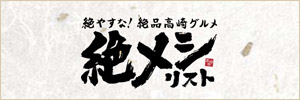本文
特別インタビュー 相内優香さん (2)
懐かしの味、ヨモギ団子にノビルの味噌和え。
群馬弁にホッとします
−例えば、家族で移住するとなると、自分目線だけでなく子どもの教育環境なども大切になってくると思います。相内さんは、どんな幼少期を過ごされたんですか?
私の住んでいた地域は、地域コミュニティがとてもしっかりしているところで、近所付き合いなどもとても活発な地域でした。小学生のときは、休みの日になると道路の真ん中にチョークで絵を描いたりとか、ご近所の家の前で寝そべっていたりしても平気で、本当にのびのび過ごしました。ご近所同士、仲も良くて。野菜が取れすぎたからっていって、もらったりするんです。東京では、なかなかないですよね。子どももたくさんいて、同い年の友だちも近所にたくさん住んでいました。近所の友だちの家に行って、つくしを摘んできて、つくしご飯をつくってもらったり、ヨモギを摘んで、ヨモギ団子をつくったり、うどんをみんなでつくったりもしました。ノビルってわかります?土手に生えている野草で、球根が食べられるんですけど、これを集めてきて、お味噌をつけて食べたりとか。本当に楽しかったな。
−高崎でも、まだまだそういうお付き合いが残っている地域がたくさんあります。
外からやってくると、「こういう付き合いが大変だ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私の家は本当に助けられたと思います。実は、私の両親も県外出身で、高崎への移住者なんです。ですから、高崎には外から来た人を受け入れる懐の深さがあると思いますし、高崎の人は移住者をあたたかく迎え入れてくれる、という実感があります。
−相内さんの話を聞いていると、とても地元のことを大切にされているんだなと感じます。
高崎には定期的に帰っていますし、いつも気にかけています。幼稚園時代、小学校時代、中学・高校のときの友人みんなとつながっています。みんなあたたかいんですよね。そうそう、人のあたたかさや、人情味が豊かな感じは高崎の特徴の一つだと思います。幼馴染とは今でもご飯を食べに行きますし、東京に出てきても、群馬出身の友だちと東京で会っています。東京に出てきて、語尾が「〇〇なん?」「〇〇なんかい?」という群馬弁を聞くとホッとします。
−群馬の人は、自分たちが方言を話しているって思っていない節がありますよね。
そうですね(笑)。仕事柄、イントネーションには気を付けていますが、数字の読み方などに特徴的なイントネーションがあったりします。