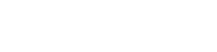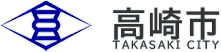本文
産業廃棄物を適正に処理するためには
産業廃棄物の処理と責任
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と決められています。(廃棄物処理法第3条第1項)
「自らの責任において適正に処理する」というのは、自ら廃棄物を処理すること(自己処理)もそうですが、産業廃棄物処理業者に処理を委託することも含まれています。
※廃棄物の処理とは、廃棄物を収集運搬する行為と処分(破砕・焼却・埋立など)する行為を指しています。
自己処理する場合は
自己処理を行うといっても、廃棄物処理法のルールに則って処理をしなければなりません。具体的には以下の3点のことであり、それぞれ基準が定められています。処理基準に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合は、廃棄物処理法の規定により処罰されるおそれがあります。
1.自己運搬の場合
産業廃棄物の収集又は運搬の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号)
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の基準(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第1号)
2.自己処分の場合
産業廃棄物の処分又は再生の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号)
産業廃棄物の埋立処分の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号)
産業廃棄物の海洋投入処分の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第4、5号)
特別管理産業廃棄物の処分又は再生の基準(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第2号)
特別管理産業廃棄物の埋立処分の基準(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第3号)
3.運搬までの保管
産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則規則第8条)
特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則規則第8条の13)
処理業者へ委託する場合は
自己処理ができない場合、事業者は産業廃棄物処理業者へ委託をすることになります。その場合は、廃棄物処理法に定められている委託基準を遵守して処理業者へ委託をしなければなりません。
産業廃棄物の処理を委託する際には、次の事項について確認し、適切に処理委託を行ってください。
※下記のほか、こちらのマニュアルも参照してください。
1.処理委託できる相手かどうかを確認すること
産業廃棄物の処理ができるものは廃棄物処理法で限られています。大部分の事業者は許可業者に処理委託をすることになりますが、その際には、委託する相手が処理委託する廃棄物を扱えるかどうかを確認しなくてはなりません。
委託する前には、許可業者の許可証を確認するのは勿論のこと、実際に業者から詳しい話を聞いたり施設見学などをして、信頼できる相手かどうかを確認してください。
なお、廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から、排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物の発生から処理が終了するまでの一連の工程が適正に行われるよう措置を講ずることが努力義務として規定されました。(廃棄物処理法第12条第7項)
2.委託料金が処理に見合った費用か確認すること
処理費用が安価であればいいというものではありません。廃棄物の処理にはそれ相当の費用がかかります。処理料金を抑えることだけを優先して、不当に安価な業者に委託した結果、委託した廃棄物が不法投棄され、委託した業者は倒産して連絡がとれず、最終的に事業者責任となって排出事業者が不法投棄の撤去費用を払うことになったケースもあります。
廃棄物を適正に処理するためにも、料金が処理に見合った費用かどうかを確認してください。
3.委託契約は必ず書面で結ぶこと
産業廃棄物の処理を委託する場合には、書面で契約書を取り交わさなければなりません。(廃棄物処理法施行令第6条の2第1項第4号)委託契約書を取り交わすのは、委託の形態によって下記の3つのパターンに分けられます。
- パターン1:産業廃棄物の運搬と処分を異なる許可業者に委託する場合
→収集運搬業者と処分業者の2者とそれぞれ契約書を取り交わさなければなりません。 - パターン2:産業廃棄物の運搬と処分を同じ許可業者に委託する場合
→収集運搬業者と処分業者が同一業者であっても、収集運搬と処分の契約書をそれぞれ取り交わす必要がありますが、収集運搬と処分に関する両方の内容を盛り込んだ1本の契約書での契約は可能です。 - パターン3:産業廃棄物の運搬は事業者自ら運搬し、処分のみ許可業者に委託する場合
→処分業者と契約書を取り交わさなければなりません。
4.産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し確認すること
事業者が産業廃棄物の処理を許可業者に委託する時には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要になります。
マニフェストには、廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名など法律で定められた必要な事項を記載して、排出事業者から許可業者に交付しなければなりません。
マニフェストは産業廃棄物の流れとともに流通するので、廃棄物が今どのような処理状況なのかが、排出事業者自らが把握して管理することができます。
5.委託契約書やマニフェストは5年間保存すること
マニフェストは、廃棄物の収集運搬、中間処理及び最終処分のそれぞれの段階ごとに、交付した排出事業者の元へ返送される仕組みになっていますが、廃棄物処理法ではこれらのマニフェストを排出事業者が5年間保存する義務が定められています。保存年限を過ぎるまで破棄しないように注意してください。(委託契約書も同様に5年間保存の義務があります。)