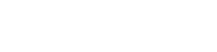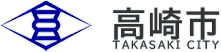本文
屋外での燃焼行為(野焼き等)はやめましょう
屋外でごみなどを燃やす行為である野焼きは、群馬県の生活環境を保全する条例(以下、県条例)で原則禁止されています。
これらの行為は、有害物質を発生させる恐れがあることはもちろんですが、煙や臭いにより、周辺の生活環境へ悪影響を及ぼし、近隣住民の迷惑となります。


家庭ごみは燃やさずに、町内会で決められたごみステーションに出しましょう。
よくあるお問い合わせ
質問1 すべての焼却行為が禁止されているのですか?
大量のばい煙を発生する次の6品目については、屋外で燃焼させてはいけません。(県条例第91条第1項、規則第53条)
- ゴム
- 皮革
- 合成樹脂
- 合成繊維
- タールピッチ類
- 不要になった油
上の6品目以外の物であっても、みだりに燃焼に伴ってばい煙が発生するものを、屋外で多量に燃焼させてはいけません。(県条例第91条第2項)
ただし、焼却設備を用いた適正な燃焼行為や地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為などは、生活環境を保全する上で支障が大きくないものとして、例外的に認められます。(県条例第91条第3項)
焼却設備を用いた燃焼行為(県条例第91条第3項第1号、規則第54条)
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800℃以上の状態で物を燃焼できるものであること
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
- 燃焼室内において物が燃焼しているときに、燃焼室内に物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ物を燃焼室に投入することができるものであること
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するために必要な助燃装置が設けられていること
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
その他の規則で定める燃焼行為(県条例第91条第3項第2号、規則第55条)
- 地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為(どんど焼きなど)
- 宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為(神社のお焚上げなど)
- 学校の教育課程として行われる活動、その他の教育活動に伴う燃焼行為(学校で行うキャンプファイヤーなど)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為、たき火その他の小規模な燃焼行為であって生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為(庭先での落葉焚きなど)
質問2 「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為」であるかどうかは、どのように判断するのですか?
周辺の迷惑にならない程度の燃焼行為かどうかということが、判断基準の一つとなります。ただ、それがどの程度の燃焼量に相当するかということは、燃焼行為の方法や周辺の環境などの様々な条件により異なるため、具体的な事例に応じて判断することになります。
質問3 近所で野焼きをされて困っています。どこに連絡したらいいですか?
野焼きの指導は、焼却の最中に実施することが最も効果的です。焼却時に環境政策課又は各支所市民福祉課までご連絡ください。メール等での連絡の場合、確認に時間を要してしまうことをご了承ください。また、火災の危険や緊急性を感じた場合は、消防署までご連絡をお願いいたします。
質問4 剪定枝や野菜の残さなどを野焼きすることも禁止ですか?
適用除外(農業を営むためにやむを得ない行為)に該当しない屋外での燃焼行為は、禁止されます。
剪定枝は直径3cm、長さ60cmまでの大きさで、一束直径30cm程度に紐でしばったもの、落ち葉や草・小枝は乾燥させたものを指定袋に入れて、3袋程度であればごみステーションに出してください。量が多い場合は、各クリーンセンターへ直接、搬入してください。(100kg以下は無料)
なお、事業系のごみはごみステーションに出せません。
関連情報
家庭ごみの分け方やゴミステーション等への出し方については、こちらをご確認ください。
県条例における屋外での焼却行為の制限については、こちらをご確認ください。
- 群馬県の生活環境を保全する条例Q&A<外部リンク>