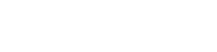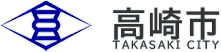本文
要介護認定の申請について
要介護認定の申請に市役所の窓口に行きたいのですが、何が必要ですか?
- 65歳以上(第1号被保険者)→介護保険被保険者証の原本(※)
40~64歳(第2号被保険者)→医療保険の加入が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)の写し 医療保険の加入が確認できるものをお持ちでない場合には情報照会を行いますので、提出者(窓口に来た方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。 - 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
(窓口にもご用意があります) - 代理人選任届(病院のソーシャルワーカー、知人、グループホーム職員等が申請する場合)
※65歳以上の方で介護保険証がない場合は、
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
- 提出者(窓口に来た方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(同一世帯員以外の方が申請する場合)
上記の申請書類を揃えて、介護保険課または各支所市民福祉課へ提出してください。
申請に必要な書類のダウンロードはどのようにできますか?
下記リンク先のページからダウンロードすることができます。
要介護認定は申請からどれくらいで結果が出ますか?
申請日から30日程度です。
市民サービスセンターでも、要介護認定の申請はできますか?
できません。申請ができるのは、市役所の介護保険課と支所の市民福祉課です。
市役所の窓口に行くことが難しいのですが、郵送申請や電子申請はできますか?
郵送申請と電子申請が可能です。
郵送申請
郵送申請の場合は、
- 65歳以上(第1号被保険者)→介護保険被保険者証の原本(※) 40~64歳(第2号被保険者)→医療保険の加入が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)の写し。医療保険の加入が確認できるものをお持ちでない場合には情報照会を行いますので、提出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しを添付してください。
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 代理人選任届(病院のソーシャルワーカー、知人、グループホーム職員等が申請する場合)
※65歳以上の方で介護保険証がない場合は、
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
- 提出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 委任状(同一世帯員以外の方が申請する場合)
上記の申請書類を揃えて、介護保険課または各支所市民福祉課宛てへ郵送してください。
郵送申請受理後、認定調査の日程調整や主治医意見書の依頼確認等で受付担当から連絡させていただきます。
電子申請(マイナポータル)
電子申請の場合は、マイナポータルからの申請を受け付けております。
以下のリンクより申請をお願いいたします。
- 要介護・要支援新規申請<外部リンク>(要介護・要支援認定を初めて受ける方)
- 要介護・要支援更新申請<外部リンク>(認定有効期間満了が近づき、更新する方)
- 要介護・要支援区分変更申請<外部リンク>(要介護・要支援認定の区分の見直しをしたい方)
申請受理完了後、マイナポータルに登録いただいたメールアドレスに認定調査の日程調整や主治医意見書の依頼等に関するメッセージをお送りしますので、ご確認をお願いいたします。
今は介護サービスを利用する予定はありませんが、将来が不安なので、一応申請しておきたいのですが。
介護サービスを利用しない場合、申請の必要はありません。心身の状態が変化して介護サービスが必要になったときに、申請してください。
要介護認定の申請後に、すぐ介護サービスを利用できますか?
要介護認定申請後、結果が出る前でも暫定利用ができます。ケアマネジャーや高齢者あんしんセンターに相談してください。
認定調査とはどのようなものですか?
自宅や病院、施設など本人の現在生活している場所に認定調査員が訪問し、日頃の生活の様子を聞き取ります。寝返りや歩行など体の動きも確認します。調査の際は、本人の生活の様子を分かっている人(家族、ケアマネジャー、施設職員など)に立ち会いをお願いします。かかる時間はおよそ1時間程度ですが、前後する場合もあります。
認定調査の際に、本人の前だと話しづらいこと(本人の認知面の問題、トイレの失敗など)があります。どうすればいいですか?
認定調査の前に、調査員から家族に日程調整の電話をします。そこで、本人の前だと話しづらいことがある旨を調査員に伝えてください。その場合、本人への聞き取り後に、別室や家の外で家族からの聞き取りを追加で行います。後日、電話で家族からの聞き取りを行うことも可能です。
更新申請の通知が届いたのですが、どうすればいいですか?
継続してサービス利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
担当ケアマネジャーがいる場合は、その人に相談してください。担当ケアマネジャーがいない場合は、本人または家族が要介護認定の申請についてのQ&Aを参考に更新申請を行ってください。本人または家族による申請が難しい場合は、高齢者あんしんセンターに代行申請を依頼できます。
ただし、現在利用しているサービスがなく、今後も利用の予定がない場合、更新申請は不要です。必要になったときに再度新規申請をしてください。
病院に入院していますが、いつ頃申請したらいいですか?
入院中でも申請が可能です。ただし、本人の状態が安定してからの申請をお勧めします。申請の目安としては、「リハビリを開始してしばらく経ち、心身の状態が安定している」「1か月以内の退院を予定している」などです。
申請が早すぎると、その時点での生活の様子に応じた結果になるため、要介護度が高く出ることが多くなります。要介護度が高いと1回あたりのサービス利用料が高くなり、本人や家族の金銭的負担が大きくなる可能性があります。
要介護認定の流れや認定後のサービス利用について詳しく知りたいのですが、参考になる資料はありますか?
市役所の介護保険課や支所の市民福祉課にて、案内の冊子「あんしん介護保険 くらしをささえる制度があります!」を配布しています。介護保険制度の概要についてから見ることができます。
複数の病院を受診していますが、主治医意見書はどこにお願いすればいいですか?
介護を要する原因となっている病気を診ている医師や、より本人の心身の状態に詳しい医師にお願いすることを推奨しています。
主治医がいません。主治医意見書はどうすればいいですか?
要介護認定には主治医意見書が必須のため、どこかの病院に記載してもらう必要があります。受診して主治医意見書を書いてもらえるか、お近くの病院に相談してください。病院が思い当たらない場合は、以下の機関に相談してください。
外部リンク
高崎市医療介護連携相談センターたかまつ<外部リンク>
高崎市医療介護連携相談センター南大類<外部リンク>