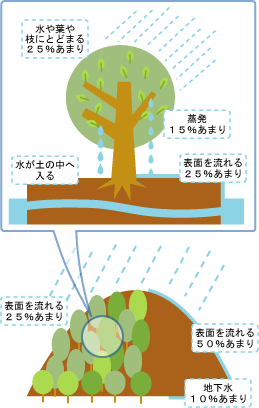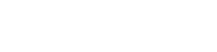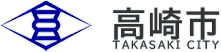ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
水源かん養林事業の概要
高崎市は、水道用水の3割弱を烏川からの取水に依存しています。この烏川の上流は、戦後の森林乱伐により水源林が減少し、大雨による増水、あるいは水量不足にみまわれるなど不安定な水源となっていました。
そのために自然のダムといわれる森林を育成し、この河川の枯渇を防止し安定した水を確保するために昭和46年当時の倉渕村の村有林145.7haを借り上げ、高芝地区において植林、下刈り、除伐、間伐を実施し、水源かん養林として森林の整備を行うことに力を注いできました。
高崎市と倉渕村の合併後からは、借り上げていた145.7haに合併前の村有林80.4ヘクタールとあわせて水源かん養林として、高崎市水道局が管理を行っています。
このように、水源かん養林として森林を整備し、管理することは、森林の持つ保水能力、水質浄化機能を向上させ、河川流量の安定確保、水質安定維持へとつながっていきます。

- 所在地:高崎市倉渕町高芝27-9外
- 面積:全体面積 226.1ヘクタール 造林面積 162.9ヘクタール
雨が降ったときに森林があると25%ほどが木の幹や葉にとどまり根からも吸収されたりしていきます。他に地面へ流れた雨水の35%ほどが地下水となり自然のダムとなりますが、木が無いと10%ほどの雨水しか地下水にならないといわれております。
また森林があることにより、木の根が網の目のように地中深くに広がり、土砂の流出をくいとめることになります。雪シ-ズンには、木々の枝や幹があることにより雪崩を防ぐ役割も果たすといわれています。